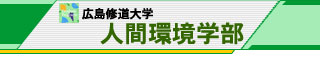


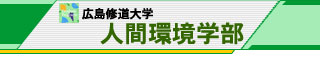 |
 |
 |
| ■講義方針 | 市民参加型のまちづくりを進めるための人材である、都市計画の専門家と住民との間をとりもつ“ファシリテーター”の育成としての都市計画論。 市民・企業・行政の協働を進めるためのワークショップ、オープンハウス等の情報公開と意識の共有化手法、都市計画専門家や行政と住民との間での意見交換等を促すファシリテーション技術やプレゼンテーション技術を、実践を含めて、学んでいきます。 また、住民の意見を知るための手段としての社会調査や、合意形成についても講義していきます。 |
|||||||
| ■講義予定 |
|
|||||||
| ■講義内容および提示資料 | ||||||||
| <第1回> ガイダンス(しあわせ感のあるまちづくり) 1 講義についての考え方 2 都市の風景(お気に入り) 3 専門ゼミナールでの都市見学(その1) <第2回> わが国の都市計画の概要、現代都市計画の歴史・経緯 (1)都市計画の概要 (2)現代都市計画の誕生経緯の説明 (3)ハワードの田園都市論~現在のわが国でのニュータウン建設との関わり 4 現代都市計画によるまちづくり PDFファイル <第3回> 改正都市計画法、都市計画の課題 <第4回> 郊外住宅地の抱えている課題 5 専用住宅の成立と郊外化について 6 住宅地の郊外化の果て <第5回> これからの郊外住宅地についてのワークショップ(1) 要素抽出 7 合意形成技法 <第6回> これからの郊外住宅地についてのワークショップ(2) 構造分析 8 千里ニュータウンの再生 <第7回> これからの郊外住宅地についてのワークショップ(3) 構造分析→対策立案 9 KJ法による問題構造分析の解析図 次回提出物:高齢者にとって住みやすい郊外住宅地の提案 ☆グループ ①問題の構造分析図(仕上げること) ②衆目評価法による評価結果(A4用紙1枚) ☆個人 ①問題の構造の説明文(A4用紙1枚) ②計画案<ポスター>(A4用紙1枚) 配布した例を参考に作成(イラストなども) <第8回> これからの郊外住宅地についてのワークショップ(4) WS体験から、ファシリテーターについて考えてみる 10 もう一度、ファシリテーターについて考える <第9回> 美しく,個性豊かなまちづくり(1)-歴史的環境の保全と生活利便性の向上の対立(鞆の浦を例に) 都市計画の実行に住民が反対することの意味を考えてみる。 11 鞆の浦 <第10回> 美しく,個性豊かなまちづくり(2) (国立のマンション訴訟から) (1) 国立マンション訴訟に見る景観問題 (2) 都市景観の実状(個人の権利と公共の福祉のせめぎ合い) 12 都市景観~個人と公共 <-ファイル容量が大きいので注意 PDFファイル <第11回> 美しく,個性豊かなまちづくり(3)(景観規制) (1) 欧米の風景計画 (2) 日本の景観規制 (3) 景観法 13 都市景観デザイン <-ファイル容量が大きいので注意 PDFファイル <第12回> 総括 14 総括 |
||||||||
| ↑このページの上へ戻る |